ホーム > 子育て・教育 > 保育所・幼稚園・認定こども園など > 認可保育所等 > これから保育所等の申し込みをしたい方 > 保育所等の申し込み方法
更新日:2025年6月25日
ここから本文です。
保育所等の申し込み方法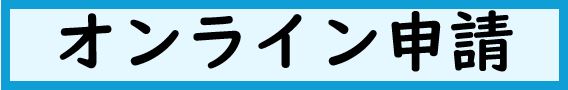
このページで案内するのは次の施設の利用申し込み方法です。
- 「保育所」
- 「小規模保育事業所」
- 「認定こども園の保育利用(2・3号)」
「認定こども園の1号(教育利用)」で利用しているお子さんが、「同じ園の2号(保育利用)」での利用を希望する場合も、新規に保育所等をお申し込みいただく方と同様の利用申し込みを行う必要があります。利用調整の結果、内定が出れば、2号(保育利用)での利用を開始することができます。
また、前年度に利用保留になっている方が、次年度以降の利用を希望する場合も、改めて利用申込みが必要です。
次の施設の利用申し込みは直接施設へおたずねください。
- 「幼稚園」
- 「認定こども園の教育利用(1号)」
- 「認可外保育施設」
令和7年度利用申込案内
令和7年4月から令和8年3月までに利用開始を希望する申し込みにあたっては、下記の「保育所等利用申込案内」をよくお読みください。
- 令和7年度鹿児島市認可保育所等利用申込案内(PDF:3,655KB)
- 第1期から第3期は、令和7年4月から保育所等を利用したい方が申込の対象です。(育児休業明けでの申込は、4月1日~6月30日に職場復帰する方が対象です。)
令和7年度申込受付期間
令和7年度保育所等利用申込の受付期間は次の通りです。
| 調整期 | 受付期間 |
|---|---|
| 第1期 | 令和6年11月1日(金曜日)~令和6年12月11日(水曜日) |
| 第2期 | 令和6年12月12日(木曜日)~令和7年1月30日(木曜日) |
| 第3期 | 令和7年1月31日(金曜日)~令和7年3月3日(月曜日) |
| 随時期 |
利用開始希望日が属する月の前々月の16日から前月の15日 (15日が閉庁日の場合は翌開庁日) 育児休業から復帰するのに併せて利用申込される方は通常の調整期 よりも前に申し込むことができます。申込時期については「保育所 等利用申込案内」をご確認ください。 |
- 申請書等の様式に変更があるため、令和6年10月25日(金曜日)にホームページに掲載または、令和6年11月1日(金曜日)から本庁保育幼稚園課、各支所保育担当窓口で配布を開始する申請書等をご利用ください。
- 保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書や診断書等)は、証明日が令和6年10月25日(金曜日)以降のものでなければ受付できません。
- 同じ調整期間内であれば、「申し込んだ順」は利用調整の結果に影響しません。(例:11月1日に申し込んでも12月11日に申し込んでも、同じ「第1期申し込み」の取り扱いで、差はありません。)
保育所等の申込方法
保育所等の利用申込みにあたっては、教育・保育給付認定(2・3号)の申請も同時に、「子どものための教育・保育給付支給認定申請書2号・3号認定用兼利用申込書」により、行います。
教育・保育給付認定(2・3号)
教育・保育給付認定(2・3号)は、保護者全員が次の「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定します。
| 保育を必要とする事由 | 必要な証明書類 |
|---|---|
| 就労(1か月60時間以上) | 就労証明書(市が定める様式) |
| 保護者の疾病・負傷 | 診断書(市が定める様式) |
| 保護者の障害 | 診断書(市が定める様式)、障害者手帳の写し(所持者) |
| 同居親族の常時介護・看護 | 介護・看護が必要な親族の診断書(市が定める様式) |
| 災害復旧 | 罹災証明書 |
| 児童虐待やDVのおそれがある | 専門機関の証明等 |
| 就学、職業訓練等 | 在学証明書、就学時間が分かるカリキュラム等の写し |
| 妊娠・出産(産前産後期間) | 母子手帳の表紙と分娩予定日が分かるページの写し |
| 求職活動(起業準備を含む) | 求職活動申立書(市が定める様式) |
対象となるお子さん
保護者が鹿児島市に住所がある、保育を必要とするお子さんです。
- 利用開始日までに鹿児島市に転入する予定のある方は、直接鹿児島市に申し込みをすることができます。
- 保護者が鹿児島市以外に居住するお子さんが、鹿児島市の保育等の利用を希望される場合は、居住地の市町村で申し込んでください。また、申込書等も居住地の市町村へお問合せください。この場合、申し込みできるのは第2期からです。
必要な書類
詳細については、各年度の「保育所等利用申込案内」を必ずご確認ください。
【全ての方に必要な書類】
- 「子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書」
- 「保育を必要とする状態を証明できる書類」(※保護者それぞれに必要です。)
【状況に応じて必要な書類】
- 「税額を証明する書類」:マイナンバーの記載および税情報の閲覧に同意しない方
- 「障害者手帳等」:精神障害者保健福祉手帳または療育手帳をお持ちの場合
- 「幼稚園教諭免許状又は保育士証の写し」:保護者が幼稚園教諭、保育教諭、保育士として幼稚園、認可保育所、認定こども園及び認可外保育施設等に就労している又は就労予定の場合
- 「看護師免許証又は准看護師免許証の写し」:保護者が看護師又は准看護師として幼稚園、認可保育所、認定こども園に就労している又は就労予定の場合
申込書等の様式のダウンロードは、「申込書等の様式」のページをご覧ください。
オンライン申請
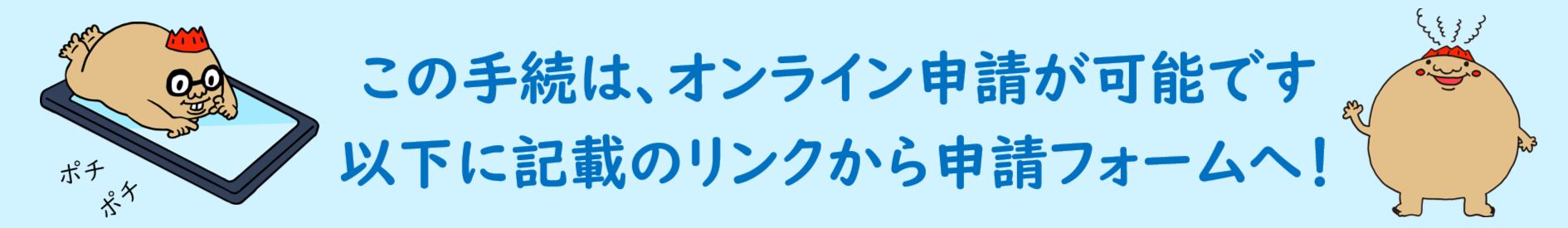
保育所等の利用申込みはオンライン申請(マイナポータルによるオンライン申請)でも受け付けています。詳しくは、「保育所等利用申込み手続きのオンライン申請について」をご確認ください。
申請受付時に、申請者の「マイナンバーの確認(番号確認)」と「本人確認書類(運転免許証等)」のできる書類の提示をお願いしております。マイナンバーカードであれば1枚で番号確認と本人確認が可能ですので交付を希望される場合は市民課又は各支所総務市民課へお問い合わせください。確認書類等については、各年度の「保育所等利用申込案内」もしくは「マイナンバー記載のお願い」のページを参考にしください。
受付場所
- 市役所(保育幼稚園課、谷山子育て支援課、各福祉課・保健福祉課へ)
- 各保育所等
- 郵送(受付締切日必着)
事前の見学
保育所等は、市や国の定めた基準のもと、それぞれの理念で保育を行っています。そのため、行事の有無や実施方法、保育料以外に必要となる費用についても施設によって異なります。利用申込みの前に、利用を希望する保育所等をお子さんと一緒に見学し、送迎にあたっての利便性や施設設備、保育に対する考え方等が保護者の方と合っているかなどをご確認ください。
見学の申込みについては、事前に直接保育所等へお問い合わせください。
お子さんの健康状態
食物アレルギーや発育、発達の遅れなど、お子さんの健康の状態について、気がかりな点やご心配がある場合、健診時や医療機関の受診時に指摘されたことがある場合は、「利用申込書」の「園への特記事項」にその旨を必ず記載してください。
障害等のため特別に配慮が必要なお子さんの利用申込み前には、希望する保育所等をお子さんと一緒に見学してください。お子さんを安全に保育できる人員と設備があるか保育所等と確認のうえ、利用申込みをお願いいたします。
医療的ケアが必要なお子さんの利用申込みは、別途ご相談が必要になります。「保育所等における医療的ケア児受入れ」のページをご確認のうえ、市窓口に直接ご相談ください。
利用調整
利用調整とは、保育所等の受け入れ可能な人数を超えた利用申込みがあり、申込者全員の利用が困難な場合は、保育を必要とする事由や家庭の状況等について点数化し、合計点の高い申込者から利用できるように、鹿児島市が調整を行うことです。
点数は、基本点数と調整点数からなり、同点の場合は、同点者調整項目表により、調整点数の合計点や就労の有無、世帯状況などで調整することになります。基本点数等は、各年度の「保育所等利用申込案内」をご確認ください。
利用調整結果のお知らせ
利用調整の結果の送付の時期については、次のとおりです。
| 調整期 | 結果のお知らせ時期 |
|---|---|
| 第1期 | 1月下旬 |
| 第2期 | 2月下旬 |
| 第3期 | 3月中旬 |
| 随時期 | 毎月下旬 |
(注)利用保留になった場合は、初回のみ「利用保留通知書」を送付します。次回以降の利用調整において、引き続き利用保留の場合は、通知されません。利用可能となった時点でお知らせします。
利用調整で内定した場合
利用調整の結果、希望した保育所等のいずれかで利用が内定した場合は「利用内定通知書」を発送します。内定した施設に連絡を取っていただき、施設での面談と健康診断の日程調整を利用開始前に行っていただきます。面談と健康診断を受けていただいた後に、正式な利用決定となります。
内定を辞退される場合は、速やかに辞退届を提出してください。
利用調整で保留(待機)になった場合
利用調整の結果、希望したすべての保育所等で利用保留(待機)となった場合は「利用保留通知書」を発送します。利用申込みは、年度内に限り次回以降も継続して利用調整を行います。保育を必要とする事由や希望する保育所等に変更がある場合、手続きが必要です。詳しくは市窓口にご相談ください。
利用保留通知は初回のみ発送いたしますので、次回以降の利用調整でも保留となった場合は通知されません。
広域利用
「鹿児島市内居住の方が他市区町村の保育所等の利用を希望する場合」もしくは「他市区町村に居住の方が鹿児島市の保育所等の利用を希望する場合」は、お申し込みいただく自治体と利用調整を行う自治体が異なることになります。詳しくは、各年度の「保育所等利用申込案内」をご確認ください。
「保育所等ガイドMAP」の配布
市役所(保育幼稚園課、谷山子育て支援課、各福祉課・保健福祉課へ)および保育所、認定こども園において「保育所等ガイドMAP」を配布しております。各保育所等の場所および公式HP等の二次元コードを掲載したマップです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください