ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 7.風水害対策に関する情報 > 土砂災害への備え
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
土砂災害への備え
鹿児島市は、シラス(火山噴出物)でおおわれており、土砂災害が起こりやすい地域です。
身近な場所に土砂災害の危険性がないか確認し、災害が起こる前に避難ができるように日ごろから心掛けましょう。
1.土砂災害の恐れがある箇所を確認する
(1)下記のマップを活用し、自宅や職場、学校周辺に土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所がないか確認しましょう。(外部リンクが開きます)
- 土砂災害警戒区域の位置確認:「かごしまiマップ(防災マップ)」(外部サイトへリンク)(避難所の確認もできます)
- 土砂災害危険箇所の位置確認:「土砂災害情報マップ」(外部サイトへリンク)(県ホームページが開きます)
- 土砂災害警戒区域とは?
土砂災害から住民の生命や身体を保護するため、土砂災害防止法に基づき鹿児島県が指定するもので、土砂災害が発生する恐れのある区域を示したものです。
土砂災害防止法に基づき指定される区域には、土砂災害警戒区域、土砂災害特別区域の2つがあります。
- 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは、土砂災害のおそれがある区域で、警戒避難体制の整備を図ることを目的として指定します。
- 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とはイエローゾーンの中でも建造物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる区域で、住宅等の新規立地の抑制等を目的として指定します。
- 土砂災害危険箇所とは?
土砂災害危険箇所とは、調査により土砂災害が発生するおそれのある箇所として整理したもので、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所に分けられます。
(2)避難場所までの経路を確認しましょう。
雨天時や夜間に避難する場合も想定しながら、マンホールや側溝などの危険な箇所がないか実際に歩いて確認しましょう。
(3)非常持出品を準備しましょう。
貴重品や非常食、衣類、常備薬など、避難時にすぐに持ち出すべき必要最低限の物品を備えておきましょう。
2.土砂災害の種類と前兆現象を確認する
|
土砂災害の主な原因 |
こんな前兆現象に注意! |
|
|---|---|---|
|
がけ崩れ |
急傾斜地(傾斜の角度30度以上で高さが5m以上のもの)において、大雨や長雨などにより、雨水が地面にしみこみ、緩んだ“がけ”が突然崩れ落ちるものです。 |
|
|
土石流 |
山や谷(渓流)の土、石、木などが、大雨や長雨等による水といっしょになって、すごい勢いで流れてくるものをいいます。 |
|
|
地すべり |
大雨や長雨などにより、雨水が地面にしみこみ、水の力によって持ち上げられた地面が広範囲にわたり、ゆっくりと動き出すものです。 |
|
3.避難情報を確認する
(1)大雨時や台風接近時は、最新情報の収集に努めましょう
- 防災行政無線自動電話案内サービス
災害発生時などに、防災行政無線で放送した内容を電話で確認することができます。(通話料は利用者負担)
◎専用ダイヤル:099-222-7222
-
防災行政無線FAX配信サービス
災害発生時などに、防災行政無線で放送した内容を、事前に登録されたFAXに配信します。
登録は、「鹿児島市防災情報FAX配信登録届出書(ワード:11KB)」をご記入の上、FAX(099-226-0748)かEメールで危機管理課までお送りください。
- 危機管理課Eメール:
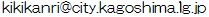
メールアドレスは迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
- 安心ネットワーク119
事前登録したメールアドレスに、災害情報、防災情報、避難情報などをメール配信します。(登録無料)
安心ネットワーク119の登録については「安心ネットワーク119」で確認することができます。
天気予報、降水予報、台風情報、火山情報などを入所できます。
大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等を補足する情報です。5キロ四方の領域ごとに、土砂災害発生の危険度を5段階に判定した結果を表示しています。メッシュ判定を参考に早め早めの避難を心がけてください。
(2)鹿児島市が発表する避難情報の内容と発表されたときに取るべき行動
避難情報等と災害時に市民がとるべき避難行動については、「令和3年5月20日から警戒レベル4避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です。」でご確認いただけます。
(注意)
近年、局地的大雨や集中豪雨などによる災害の発生が増えています。災害が迫ったとき、おかれた状況は一人ひとり違います。
鹿児島市からの避難情報が発生されていなくても、それぞれが自ら判断し、身の危険を感じたら早めの避難を心がけましょう。

(注)危険が切迫している場合は、指定された避難所への移動(1水平避難)だけでなく、建物の2階以上に一時的な避難(2垂直避難)をすることも検討してください。
(3)避難情報の伝達方法
防災行政無線、広報車両、安心ネットワーク119、緊急速報メール、テレビ、ラジオなどの手段で市民の皆様に伝達します。
鹿児島市防災専門アドバイザリー委員である、鹿児島大学農学部教授の地頭薗先生に風水害についてお聞きしました。

-
質問1
平成29年7月九州北部豪雨のように、近年、全国的に集中豪雨や台風による被害が目立ちますが、近年の気象状況に変化があるのでしょうか。
- 回答1
九州北部豪雨では、大雨特別警報が発表されましたが、福岡県朝倉市において1時間降水量129.5ミリ、日降水量516.0ミリの大雨を記録しました。豪雨によってたくさんの崩壊が発生し、多量の土砂・流木と洪水による大災害となりました。
気象庁の資料によると、1976年~2016年においてアメダス1000地点あたりの1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数は、10年あたり約20回の割合で増加しています。地球温暖化の影響と言われていますが、極端な気象現象の頻度や規模は今後も増加することが心配されています。
-
質問2
自宅が川の近くや崖下に建っている場合など、どのようなことに気をつければいいですか。
- 回答2
まず、自宅周辺の状況を「防災マップ」を使って調べましょう。土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域がなぜ指定されているのか、地域全体を見て考えてみましょう。また、異変に気付くためには、日頃から周辺の様子をよく見ておくことが大事です。たとえば、崖が近ければ、斜面の土や石が浮き上がっていないか、亀裂がないかなどを調べましょう。また、川が近ければ、水位を確認する目安を決めておくのも重要です。いざという時の避難所と避難経路を確認し、気づいたことを防災マップに書き入れ、「マイ防災マップ」へ進化させましょう。
-
質問3
毎年、梅雨を迎える前に、家族で点検しておくべきこと等がありましたら、教えてください。
- 回答3
私たちにできる防災で大事なことは、「日頃の備え」と「早めの避難」です。自宅周辺の危険箇所、避難所と避難経路、家族に必要な非常持出品など、日頃から話し合っておきましょう。大雨の時は気象情報に注意し、早めの避難を心がけましょう。最近は突然の豪雨で避難が困難な場合もあります。そんな時は、家の中でより安全な場所、たとえば、崖と反対側の部屋への移動を考えなければなりません。そのためにも、日頃からいくつかの避難方法を話し合っておくことが重要です。それによって、いざという時に適切な判断ができます。
-
市民の皆様へメッセージ
自分の命は自分で守る「自助」が防災の基本です。さらに隣近所で助け合う「共助」も大切です。「自助」と「共助」と行政の助け「公助」の3つを連携させて災害に強い地域をつくりましょう。防災で大切なことは「正しい知識を持ち、正しく恐れ、正しく防ぐ」、このことが自分を守り、地域を守ることになります。
5.指定避難所などを確認する
- 鹿児島市の指定避難所などを確認する(←クリック)
- 自主的に避難するときには、鹿児島市役所(代表099-224-1111)又は、地域福祉課(099-216-1244)にご連絡ください。
(※夜間や土曜日、日祝日は、鹿児島市役所(代表099-224-1111)にご連絡ください) - 地域によっては、指定避難所が離れたところにあり、避難の途中で危険に遭遇することも考えられますので、指定避難所以外にも身近に避難できる安全な場所を探しておきましょう。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください