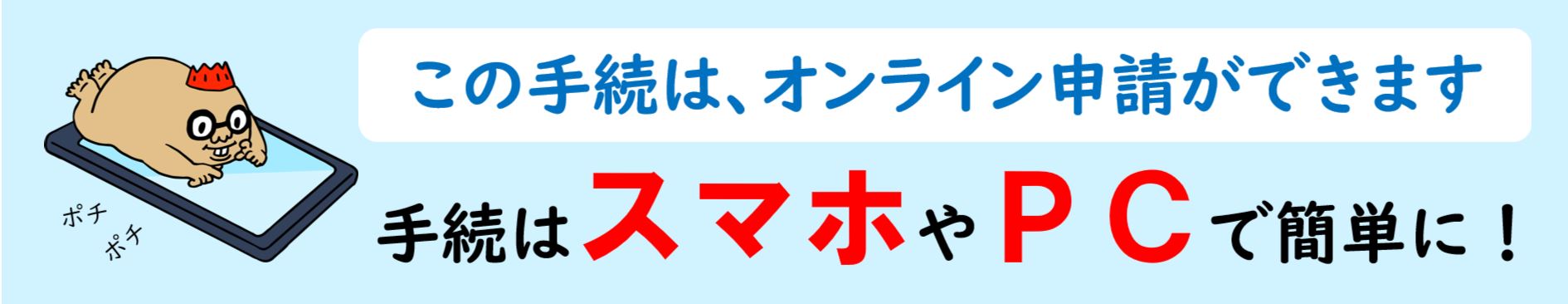ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援の手当・助成 > こども医療費助成制度
更新日:2025年8月27日
ここから本文です。
こども医療費助成制度
令和7年4月1日診療分から制度が拡充されました
令和7年4月1日から、市町村民税課税世帯の中学3年生までのこどもは、県内医療機関等での保険適用分にかかる窓口負担がゼロとなりました。(市町村民税非課税世帯はこれまでどおり高校生年代まで窓口負担ゼロです。)
1.こども医療費助成制度の目的
こどもの健康と健やかな育成を図るため、こどもの保険診療による医療費の一部を助成しています。
2.助成を受けることができる人
次の条件がすべてそろっていることが必要です。(所得制限はありません)
- 鹿児島市内に住所を有する中学3年生までのこども(市町村民税非課税世帯は18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども)
・中学3年生とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもです。
・15歳に達する日とは、15歳の誕生日の前日のことです。 - 健康保険に加入しているこども
- 生活保護等、他の医療扶助を受けていないこども
3.受給者証の交付
対象のこどもの保護者は、受給資格の申請をして、受給者証の交付を受けてください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
- 健康保険の加入が確認できるもの・・こどもの名前が記載されているもの(コピー可)
(例)マイナポータルからダウンロードした資格情報画面、資格確認書、資格情報のお知らせ、令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証(マイナ保険証では健康保険の資格確認ができませんのでご注意ください。)
- 預金通帳等・・受給者(=保護者)名義の普通預金口座(キャッシュカード可)
- 窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類
(注)市外から転入された方で、市町村民税非課税世帯の方は、申請者(=保護者)及び同世帯の方(高校生以下は除く)の「マイナンバーカード」が必要です。
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送で交付します。
4.助成の範囲
助成の対象となるもの
保険診療による一部負担金の額
助成の対象外となるもの
- 保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療、選定療養費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)、入院時の食事代やベッド代等
- 付加給付金
- 高額療養費
- 法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費助成事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷、疾病に対する給付金)、就学援助制度による医療費援助等
5.助成を受ける手続き
県内の医療機関等を受診する場合
医療機関等の窓口で受給者証を提示してください。保険適用分の窓口負担はありません。
その他の場合
治療用の補装具を作った場合(※)や県外の医療機関等を受診する場合、県内の医療機関等でも受給者証を提示しなかった場合は、いったん医療機関等の窓口で医療費をお支払いいただき、助成金支給申請書に領収書を添付して、市役所へ申請してください。
(※)治療用の補装具を作った場合(※)は、装具の領収書のほかに、医証又は作成指示書(医療機関等で発行)、支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付し市役所に提出してください。
- 領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療による一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもので、上記の記載がないレシートでは申請できません。
- 申請は、市役所の窓口又は8.電子申請、9.郵送申請で行うことができます。
6.助成金の振込み
県内の医療機関等で「こども医療費受給者証」を提示した場合
振込はありません。(市が各医療機関に助成します。)
市役所の窓口に助成金支給申請書(領収書添付)を提出した場合
- 原則、提出した月の翌月の20日に登録口座へ振り込みます。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)なお、原則として、当月診療分の申請書は、受付できません。
- 助成金の申請期限は、診療を受けてから1年以内です。期限を過ぎると、助成金の支給は受けられませんのでご注意ください。(4月に診療を受けた場合、その医療費の助成金は翌年の4月末日が申請期限となります。)
- 審査の結果、別途提出が必要な書類がある場合は、必要な書類の提出についてご案内し、提出後の振り込みとなります。
7.届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要です。届出は、市役所の窓口又は8.電子申請、9.郵送申請で行うことができます。
|
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
手続きの内容 |
|---|---|---|
|
受給者を変更するとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (注)振込先口座の変更も必要です。 |
受給者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
|
健康保険証が変わったとき |
受給者証、こどもの健康保険の加入が確認できるもの、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
|
|
振込先口座を変更するとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (口座の変更・解約後に届出がない場合、支給日に振込みができませんのでご注意ください。) |
登録された口座情報の変更を行います。 受給者証は継続して使用できます。 |
|
受給者証をなくした、または破ったとき |
こどもの健康保険の加入が確認できるもの、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を再発行します。 |
|
受給資格を喪失するとき |
受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を返還していただくか、ご自身で破棄してください。 |
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状(PDF:367KB)を持った別世帯の代理の方からの届出については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの届出については、受給者証を郵送により交付します。
8.オンライン申請 
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルへログインし、こども医療の各種申請について電子申請を行うことができます。オンライン申請を希望される方は、次のマイナポータル外部サイトをご利用ください。
9.郵送申請
紙で郵送申請される方の申請様式は「こども医療費申請書」のページをご覧ください。
10.受診が必要か判断に迷ったときは
県が、休日や夜間における子どもの急な病気やけがについて、看護師等が応急処置や医療機関の受診の必要性などの助言を行う「小児救急電話相談」を実施しています。
鹿児島県小児救急電話相談(#8000)(外部サイトへリンク)
【その他本市の関連リンク】
問い合わせ先
こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください